はじめに(必ずお読みください)

ここで提供するのは「サイコパス(心理学上は psychopathy と呼ばれる特性)」に関する傾向セルフチェックであり、医療・臨床上の診断ではありません。正式な評価(例:PCL-Rなど)は専門の訓練を受けた臨床家のみが実施できます。本チェックは自己理解とコミュニケーション改善のきっかけとしてご利用ください。結果に不安がある場合は、医療・心理の専門家へご相談ください。
サイコパス傾向セルフチェック(簡易)
当てはまる項目にチェックを入れてください。(※ブラウザ上でカウントできます)
チェック数をカウントしてください。多いほど、その傾向を自覚的にケアする必要があります。 リセット
判定の目安(あくまで参考)
| チェック数 | 解釈(参考) |
|---|---|
| 0~2 | 特筆すべき傾向は低いと考えられます。一般的な自己理解・対人配慮を継続。 |
| 3~5 | 一部の状況で相手の感情やルール軽視が出やすい可能性。場面別の対処を学ぶと◎ |
| 6~8 | 対人場面での衝動性・共感の不足・責任回避が人間関係に影響している恐れ。専門的な助言を検討。 |
| 9~10 | 自己や他者に不利益が生じるリスクが高い範囲。臨床心理士・精神科等の専門家へ相談を推奨。 |
コミュニケーション改善のヒント
このチェックは“レッテル貼り”ではなく、行動を変えるヒントを見つけるためのものです。もし複数項目が当てはまるなら、次のステップを少しずつ実践してみてください。
感情ラベリングを習慣化
相手と自分、それぞれの感情に名前をつけて口に出します(例:「いま、苛立っている/不安を感じているね」)。言語化は衝動性を下げ、配慮ある選択につながります。
“一呼吸”ルール
反射的な反論・決定の前に3秒の沈黙。質問→要約返し→自分の意見の順で話すと、操作的に受け取られにくくなります。
フィードバックをもらう
信頼できる同僚・友人に「今日の話し方の良かった点/改善点を1つずつ教えて」と依頼。外部視点は自己認識のズレを埋めます。
ルールの“意味”を理解する
単なる禁止事項ではなく、ルールが守られることで誰の負担が減るのかを具体化。目的理解は遵守率を上げます。
専門家のサポート
対人関係でトラブルが続く、怒りや衝動が抑えにくい、罪悪感が薄く困っている場合は、臨床心理士・精神科での相談を検討してください。自己や他者の安全が脅かされる恐れがあると感じたら、今すぐ地域の相談窓口や医療機関へ。
まとめ
サイコパス特性は「ある/ない」の二分法ではなく、連続的な傾向として理解するのが実用的です。チェック結果はレッテルではなく、行動を整える指針。感情の言語化、間(ま)の活用、フェアなルール理解とフィードバックの習慣化で、対人インパクトは必ず変えられます。まずは今日の会話から、一呼吸→要約返し→提案の順で試してみましょう。
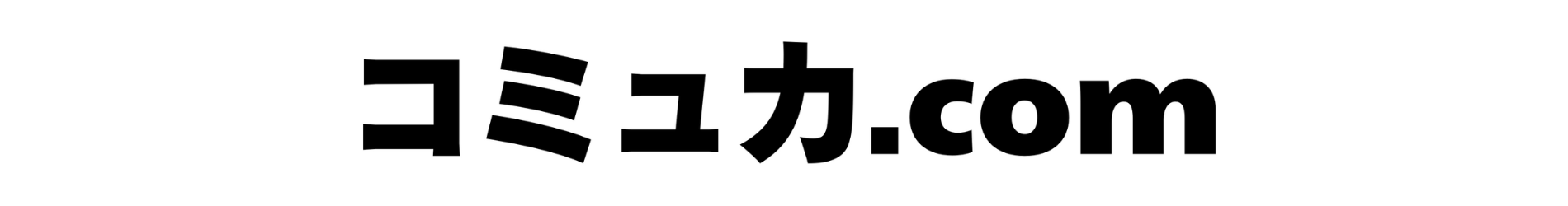
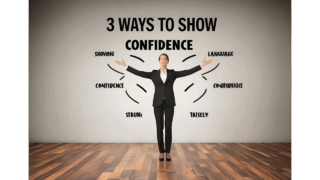
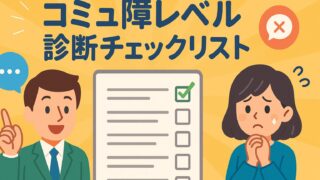

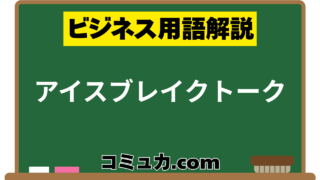

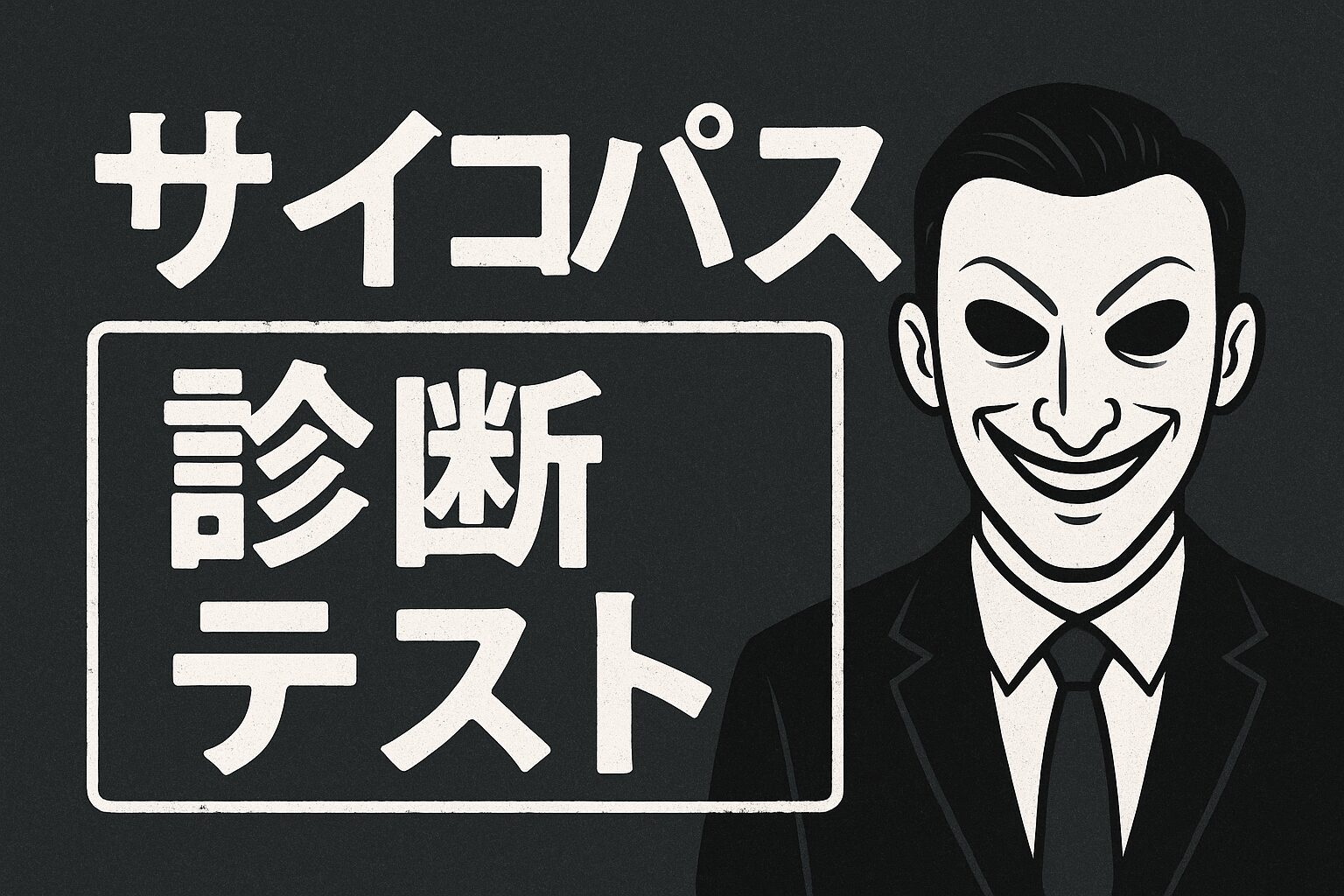
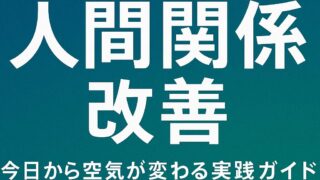

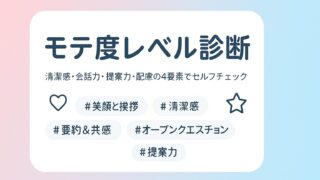

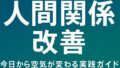
コメント